国内で化学品を取り扱う企業が保有するSDSの中には、旧JIS規格で作成されたものや、GHS分類が不完全なままになっているもの、あるいは作成時と比べて法規制が変わっているものが多数存在します。
安全データシート(SDS)は、労働安全衛生法(安衛法)やPRTR法などの国内法令で作成・提供が義務付けられており最新のGHS基準(JIS Z 7253/7252)に適合していないSDSを放置することは、重大なコンプライアンス違反となります。
なぜなら、SDSの更新は単なる文書の書き換えではなく、最新の科学的データ、日本の国内法令、そしてJIS規格のすべてを統合する高度な専門知識が必要だからです。
本記事では、既存の日本語SDSを最新のGHS規格(JIS Z 7253/7252)に完全に適合させ、法的なリスクを排除するために、実務者が踏むべき6つの専門的なステップと、そこで必要とされる高度なハイブリッド知識を解説します。
1. なぜ「古いSDSの放置」が危険なコンプライアンス違反になるのか
1-1. GHS分類の「最新性」という落とし穴
GHSの分類基準は、国連GHSの改訂(約2年ごと)に追随して日本のJIS Z 7252も随時更新されています。
-
古いSDSのリスク: 5年前に作成されたSDSが、その後改訂されたJIS Z 7252の新しい分類カテゴリーを反映していない場合、日本では表示義務がある危険有害性情報が抜け落ちることになります。
-
法令との不整合: 労働安全衛生法がSDS・ラベル交付義務対象物質を追加したにもかかわらず、古いSDSが更新されずに放置されていると、法令遵守義務を怠ったと見なされます。
1-2. 混合物の分類における「再評価と判断」の壁
SDS作成の難しさの核心は、混合物(複数の化学物質の組み合わせ)の分類にあります。
混合物の危険有害性をGHS基準で分類するには、個々の成分の毒性データ(LD50、LC50など)を基に、「最新の混合物の分類原則」(濃度カットオフ値、加算法など)に従って計算分類を行う必要があります。
既存のデータや計算結果が最新のJIS基準に適合しているかの「再評価」は、化学的・毒性学的知識に基づいた高度な判断が必須であり、古い知識や汎用的なAIでは代替できる領域ではありません。
2. 実務ステップ①:SDS作成の根幹、最新GHS分類の「再評価と再構築」
既存の日本語SDSはあくまで出発点です。最新の日本のGHS(JIS Z 7252)に適合させるためには、対象物質・混合物を最新の公的データとJIS基準で「再評価・再分類」する必要があります。
2-1. 分類に必要な最新データの収集と裏付け
分類の裏付けとなるデータの収集が、最初の専門的な作業です。
-
既存データの確認: 既存SDSに記載されている物理化学的データ、毒性データ(LD50、LC50など)が最新の文献値やデータベース(NITEなど)と照合し、依然として有効かを確認します。
-
文献値の再評価: 収集したデータを最新のJIS Z 7252の分類基準(カットオフ値など)に照らし合わせ、分類カテゴリーの変更がないかを厳密にチェックします。
2-2. 混合物分類の厳密な再実行
特に混合物の分類は、以下の厳密なプロセスが必要です。
-
成分濃度: 既存SDS記載の成分濃度に変更がないか確認。
-
成分の最新GHS分類: 個別成分のGHS分類データを最新のJIS Z 7252で確認します。
-
計算分類: 最新の濃度と毒性データを基に、JIS Z 7252の混合物分類原則を適用して、最終的な分類カテゴリーを算出します。
この再評価と再分類の過程が、SDS全体の信頼性を左右します。
3. 実務ステップ②:JIS Z 7253準拠16項目フォーマットへの「情報補完と統一」
GHSに適合したSDSは、JIS Z 7253(GHSに基づく化学品の安全データシート—内容及び表示項目)に定められた16項目の構成と記述要件に厳密に従う必要があります。古いSDSや独自のフォーマットを使用している場合は、徹底的な統一が必要です。
-
項目構成の統一: 既存のSDSを最新のJIS Z 7253の16項目に完全にマッピングし、項目のタイトルや順番を統一します。
-
必須情報の補完: 特に「15. 適用法令」や「3. 組成・成分情報」は、作成時と比べて法令が追加・変更されている可能性があるため、日本の最新法規制に基づいた情報補完が必須です。
4. 実務ステップ③:GHSラベル要素の「定型文厳守」と危険有害性情報の抽出
再分類の結果に基づいて、GHSの核となるラベル要素(絵表示、注意喚起語、H文、P文)をSDSに記載します。
4-1. H文(危険有害性情報)とP文(注意書き)の「最新定型文」厳守
H文とP文は、最新のJIS Z 7252/7253で定められた「定型文」を使用する必要があります。
-
自己流の翻訳・記載の禁止: 既存のSDSに記載された表現を流用したり、勝手に解釈した表現を使用したりすると、定型文の厳密な法的・技術的意味が変わってしまい、誤った安全情報の伝達につながります。
-
コードと文言の整合性: Hコード、Pコードが、最新のJIS規格の文言と完全に一致しているかを厳密に確認しなければなりません。
4-2. ラベルとSDSの整合性の確保
SDSの「2. 危険有害性の要約」に記載された分類、絵表示、注意喚起語が、製品のラベル表示と完全に一致している必要があります。この二つの文書間で不整合が生じると、法令違反のリスクが高まります。
5. 実務ステップ④:日本の国内法令(安衛法、化審法、PRTR法)との「再統合と確認」
GHS適合SDS作成において、最も高度な専門知識が求められるのが、「15. 適用法令」の最新情報への更新です。
-
安衛法(労働安全衛生法): 譲渡・提供時のSDS交付義務対象物質が追加されていないか、既存の対象物質の区分に変更がないかを再確認します。
-
化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律): 優先評価化学物質、第二種特定化学物質など、法規制上の区分が最新情報に基づいているかを厳しくチェックします。
-
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律): 対象物質や届出の義務に関する情報に変更がないかを確認します。
これらの法令情報は、SDSの「作成時」ではなく「最新」の情報に基づいている必要があり、既存のSDSの流用は非常に危険です。
6. 実務ステップ⑤・⑥:最新JIS規格への追従と専門家の最終チェック
6-1. 規格改正への恒常的な対応
GHSとJISは常に更新されています。企業は、SDSのメンテナンスサイクルを確立し、最新規格へのアップデートを恒常的に行う体制を構築しなければなりません。
6-2. 最終チェックの「ハイブリッド専門性」
GHS適合SDSの最終チェックでは、以下の3つの専門性を備えた多角的な検証が不可欠です。
化学・毒性学: 分類とデータが科学的に正しいか。
-
法規制コンプライアンス: 日本の最新の安衛法・化審法・JISに準拠しているか。
-
SDS言語学(定型文): H文・P文が最新の定型文通りに厳密に記載されているか。
このすべての知識と監視能力を持つ人材は極めて希少です。多くの企業がこのリスクと負担を回避するために、SDS作成・更新を外部の専門家集団に委託しています。
結論:SDSの適法性は「最新知識の有無」で決まる
既存の日本語SDSをGHSに適合させる作業は、「最新の法規制と科学的データを正確に読み解き、JISの定型に則って書き換える」という非常に高度な作業です。古い知識や曖昧な認識で作成されたSDSは、法的なリスクの源泉となり得ます。
当社は、この複雑なSDS適合プロセス全体を、最新の法規制情報を反映させながら支援いたします。専門性の高いSDS適合について、ぜひご相談ください。
WIPジャパンのGHS法規制調査サービスは、お客様の海外展開を成功に導くための強力な羅針盤となります。
合わせて読みたい関連記事 📚
既存のSDSを最新規格に適合させる作業は、最新の法規制を把握することと、外部の専門家を適切に活用することが成功の鍵です。さらなる戦略的な視点と、サービス選定のポイントをご紹介します。
1. 適合作業の「羅針盤」となる法規制調査
SDSの適合作業の前提として、常に最新の法規制情報を得ておく必要があります。その調査を戦略的に行う方法とは?
GHS対応のための法規制調査:グローバル展開を成功に導く戦略的羅針盤
規制対応の労力を削減し、正確性を高めるためのグローバルな法規制調査の進め方と、戦略的なアプローチを解説しています。
2. 法改正リスクを回避する専門監修
日本のGHS適合において、薬機法やSDSの法改正に遅れず対応できる専門家の価値は計り知れません。
薬機法・SDSの法改正に対応|規制コンプライアンス専門監修の戦略的価値
頻繁な法改正リスクを排除し、コンプライアンス体制を強固にするための専門監修の必要性とその戦略的な価値を解説します。
https://japan.wipgroup.com/media/kisei-compliance-yakkiho-sds
3. 専門業務を委託する際のパートナー選び
自社でのSDS作成・更新が困難な場合、外部に委託することが最善策です。信頼できる専門サービスを選ぶための視点とは?
製品安全データシート(SDS)翻訳サービスの選び方とポイント
規制適合のための高度なスキルを持つ専門サービスを、どのように見極め、選定すべきか。サービス選定の際のチェックポイントを解説します。



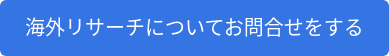


















Nov. 25, 2025