インバウンド需要のニュースを耳にするようになってから久しいですが、他の国ではどのような観光ビジネスがあるのでしょうか。本記事では、サステナブルな独自の哲学で富裕層を魅了するブータン、K-カルチャーやカジノと観光を融合させる韓国、そして富裕層向け地方長期滞在型と大型新規プロジェクトで新たなステージを目指す日本、という三カ国の観光ビジネスに焦点を当てます。
1. ブータン:ハイバリュー・ローボリューム戦略
ヒマラヤ山脈の麓に位置するブータンは、「国民総幸福量(GNH)」という独自の哲学に基づきながら、観光客数を抑えて自然環境や伝統文化を損ねない「ハイバリュー・ローボリューム(高付加価値・少量)」を掲げた観光政策を長年貫いています。
観光税(SDF)
その中核をなすのが、外国人観光客に課される「持続可能な開発料金(SDF:Sustainable Development Fee)」、観光客に1日100ドルの税金を課しています(国籍・年齢・滞在期間により一部異なる)。この料金は、ホテル代や食費とは別に徴収され、自然環境や文化遺産の保護、教育や医療といった公共サービスに充てられます。オーバーツーリズムを防ぎ、貴重な自然と文化を持続可能な形で未来に継承する目的があります。なお、コロナ流行前は1日200ドルが課せられており、2027年8月31日までの期間限定で1日100ドルとなっています。
ラグジュアリーホテルと自然体験
旅行者数を制限する一方で、高額な料金に見合うだけの体験を提供することを試みており、ブータンでしか味わえない体験を求める富裕層が必然的に多くなります。ホテルもラグジュアリーかつ自然を満喫できる長期滞在を提供しているところが目立ちます。
外資系の「ルメリディアン・パロ,リバーフロント(Le Meridien Paro, Riverfront)」や「アマンコラ ティンプー(Amankora Thimphu)」、国内資本初の5つ星ホテル「ジワリン ヘリテージ(Zhiwaling Heritage)」などが有名です。
・ルメリディアン・パロ,リバーフロント:
https://www.marriott.com/ja/hotels/pbhpr-le-meridien-paro-riverfront/overview/
・アマンコラ ティンプー:
https://www.aman.com/ja-jp/resorts/amankora/accommodation/lodges/thimphu
・ジワリン ヘリテージ:
https://www.zhiwalingheritage.com/
多言語対応
ブータンの多言語対応は、「公認ガイド」の存在が大きいといえます。原則として、ブータンの個人旅行は、政府認定の旅行代理店を通じたパッケージツアーとなります。その一環として全行程に公認ガイドが同行します。多くの観光客は入国から出国まで、日本語を含む外国語に堪能なガイドと共に行動するため、言語の心配はほとんどないといえます。
また、ブータンでは公用語がゾンカと英語のため、観光業に関わる人々の英語力は高い水準にあり、標識やメニューもゾンカと英語の併記が基本となっています。人的サービスによって言語の壁を解消しているといえるでしょう。
課題
高額なSDFによる客層の限定、SDFの価格変動による観光ビジネスへの影響、また、観光客が首都ティンプーやパロ周辺に集中していることから、地方への経済効果が限定的となる課題があります。
2. 韓国:エンターテインメントとビジネスの融合
韓国の観光政策は、エンターテインメントとビジネスという二つの強力なエンジンを組み合わせることで、多様な目的を持つ旅行者を惹きつけ、観光消費額の最大化を図っています。
コンテンツツーリズムとMICE
世界を席巻するK-POPやドラマ、映画といったK-カルチャーを観光資源とした「コンテンツツーリズム」は大きな効果を発揮しており、人気ドラマのロケ地、アイドルグループゆかりの地にファンが訪れます。韓国の化粧品や美容整形は世界的にも有名で、美容医療のツーリズムも人気です。
また、韓国は、MICE(Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition/Event)の誘致に国を挙げて取り組んできました。MICEの誘致に効果を発揮したといわれているのが、「KOREA UNIQUE VENUE」の選定です。選定された施設は、従来の会議場やホテルではなく、美術館や歴史的建造物など、韓国ならではの魅力や特別感を持つ施設です。
ICCA(国際会議協会)の2024年国際会議統計によると、開催件数は国別では韓国より日本の方が上回っていますが、都市別では東京よりソウルの方が多くなっています。
(参照:https://mice.jnto.go.jp/assets/docs/news/icca2024_jp.pdf)
カジノと統合型リゾート
さらに、ソウルには外国人観光客向けの公認カジノが複数あります。特に「パラダイスシティ(파라다이스시티)」や「インスパイア・エンターテインメント・リゾート(인스파이어 엔터테인먼트 리조트)」などのIR(統合型リゾート:カジノ・宿泊施設・レストラン・MICE施設・ショッピングモールなどが集まった複合施設)が有名です。法律上、ソウルのカジノはすべて外国人のみ入場が許可されており、日本より一足早く、カジノ産業が観光ビジネスに関わっています。
・パラダイスシティ:https://www.p-city.com/
・インスパイア・エンターテインメント・リゾート:https://www.inspirekorea.com/ja
多言語対応
多様な国からの観光客を受け入れる韓国は、多言語対応をシステムとして整備しています。7言語以上・24時間対応の観光案内電話/テキストチャット「1330」が有名です。
(参照:https://japanese.visitkorea.or.kr/svc/contents/contentsView.do?vcontsId=140643)
都市部や観光地の公共交通機関では、4カ国語の案内表示が基本で、飲食店の注文用タブレットや地図アプリなど、ITを駆使して利便性を高めているといえるでしょう。
課題
K-カルチャーの流行り廃りの影響や医療トラブルの問題、MICEの開催地がソウルに集中していること、また、カジノがもたらす社会的側面などの懸念が考えられます。
3. 日本:富裕層向け長期滞在型の観光体験、ユニークな大型施設の開発
日本では今、インバウンド需要の完全復活と円安を背景に、外資系を中心にラグジュアリーホテルの開業ラッシュが続いています。
富裕層向け地方長期滞在型
少し前までこうしたラグジュアリーホテルは都市部にできることが多かったのですが、昨今は地方が注目されています。とりわけ地方における、富裕層向け長期滞在型の観光ビジネスが目立ちます。宿泊施設については、以下のものがあります。
・Zenagi:長野県・木曽郡の古民家を再生した1日1組限定の体験型ラグジュアリーホテル
・NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち:酒蔵などを改修した客室が町に点在する分散型ホテル
(https://www.naramachistay.com/)
・ベネッセハウス:香川県・直島の自然・建築・アートの共生がコンセプトのホテル
(https://benesse-artsite.jp/stay/)
・オーベルジュ土佐山:「地産地消」の食文化を体験できるオーベルジュ(宿泊施設付きレストラン)
(https://www.orienthotel.jp/tosayama/)
ユニークな大型施設
ホテルだけではなく、テーマパークなど大型施設の建設も行われており、2025 年7月25日に沖縄県北部の世界自然遺産「やんばる」の地に、大型テーマパーク「JUNGLIA(ジャングリア)」が開業しました。「Power Vacance!!(パワーバカンス)」をコンセプトに、圧倒的な大自然を活かしたジップラインや、気球、恐竜から逃げるアトラクションなど、ユニークな体験を打ち出しています。
多言語対応
公共交通機関や観光地の案内板(主に日・英・中・韓)、また、公式アプリなどが多言語で提供されています。都市部や観光名所では多言語対応のインフラが整備されている一方、地方や小規模な店舗では多言語対応やアプリ、電子決済の普及が遅れています。また、地方では人的リソース不足が目立ちます。
課題
懸念点として、外資への依存度の上昇、大規模施設の開発とその収益確保、特に地方における人材不足などがあげられます。また、一部に観光地側と海外観光客との問題も生じています。自然環境や文化遺産の保護は、十分にできていないのが現状です。
ブータン・韓国との比較
・ブータンとは異なり、日本の観光税は「国際観光旅客税(出国税)」として出国1回につき1,000円の徴収に留まります。
・自然環境や文化遺産の保護、観光ルールについては、海外観光客にも周知が進められているものの、ブータンほどは浸透していません。
・韓国はKカルチャーですが、日本も以前よりアニメやゲームなどコンテンツツーリズムの活性化が国をあげて進められてきました。MICEについて、日本にもユニーク・ベニューがあり、迎賓館赤坂離宮やモエレ沼公園、山形美術館が有名です。万博を契機としてMICEが活発化している大阪において、「Japan MICE EXPO 2025」が2025年11月に開催されます。
・カジノについては、2018年「特定複合観光施設区域整備法(IR実施法)」が成立後、大阪にて2029年秋~冬頃の開業を目指して整備が進められています。
まとめ
ブータンが「人」を介して高品質で唯一無二の体験を演出し、韓国が「システム」による網羅的な情報提供で多様なニーズに応える一方、日本は「富裕層・地方・長期滞在」「大型施設の新設」といった方向に舵を切りながら「人」と「システム」の最適な融合を探っています。
ターゲット層も多言語対応のアプローチもそれぞれ異なります。特に高付加価値な体験を提供する上では、言語の正確さだけでなく、ターゲット層の習慣に根差した質の高いコミュニケーションが求められます。以前は国や文化圏ごとで考えられていましたが、それ以外にもターゲット層は細かく分かれており、用いる表現方法も各言語で様々です。
これら事例から、現代の観光ビジネスは画一的なものではなく、それぞれの国や地域が持つ価値をいかに戦略的に磨き上げ、顧客に届けるかが成功の鍵であるといえるでしょう。



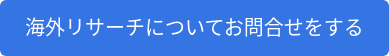















Oct. 08, 2025